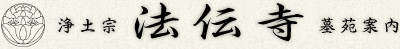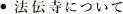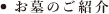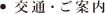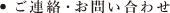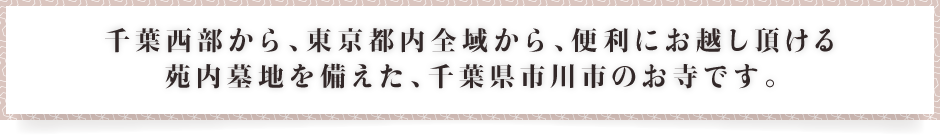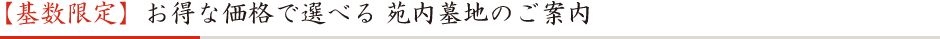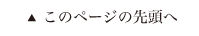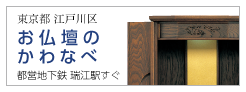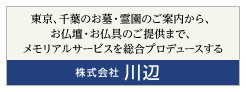法伝寺墓苑をご案内する、東京都江戸川区の石材店、株式会社川辺からのご案内
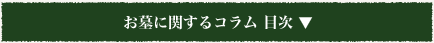
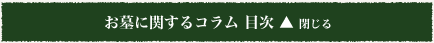
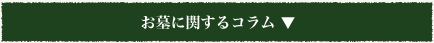
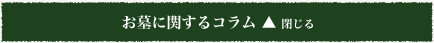
浄土宗の年中行事(4)
10月15日
十夜法要。お十夜
元来は、平貞国が京都の真如堂で行った10日間の『おこもり』が起源となっています。後に鎌倉光明寺の観誉裕崇上人が後土御門天皇の勅命を受けて行われてから、全国の寺院にも広がって行きました。現在では3日や1日という様に短くなっています。
その他
「開山忌」
日は各寺によって異なります。昔は山を切り開いて寺院を建立したことから、それぞれのお寺を創立した僧侶を開山上人と呼び習わします。お寺によっては、これを記念した開山堂や、開山上人以下、歴代の住職の位牌などを安置した位牌堂などがある場合、それらで祭事が行われることが一般的です。
「授戒会」
戒名は死んでから付けられるのでは無く、本来は生きている内に授けられるべきものです。浄土宗における授戒式は、まず観戒師から授戒についての教えを受け、教授師から儀式の指導を受け、伝戒師から戒を受け、戒名を記した戒牒を頂いて終了します。必要な日数は7~1日と様々ですが、これら三師は各寺院の住職が兼ねて行われることが多い様です。
「五重相伝」
浄土宗の信仰を深める為の講習会の様なものです。季節の良い頃に8日程の期間をかけて行われます。修了者には「誉号」が授与され、これは法名にも○誉□□という形でつけられます。また、生前に、この五重相伝をうけられなかった場合、その功徳を回向する「贈五重」という制度もあります。
※この投稿は、墓苑に関する一般的な知識の普及を目標にしています。当寺に関するご案内ではございませんので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
お墓を購入するってどういうことですか?
そのお墓を「使用する権利」を購入することです。墓地の使用権は永代で受け継ぐことができます。(一部区画を除く)その権利を墓地使用権といい、その費用を特に「墓地使用料」といいます。
浄土宗 法伝寺 墓苑案内 - 川辺 Copyright(c) 2013.Hodenji Boen Annai .All Rights Reserved.