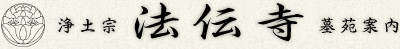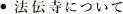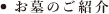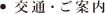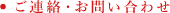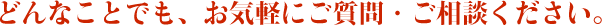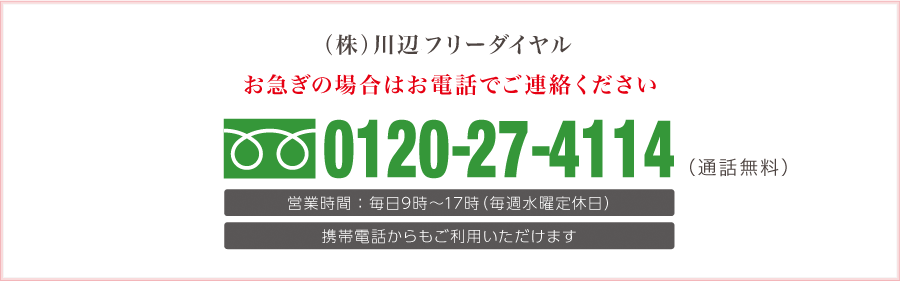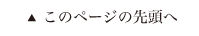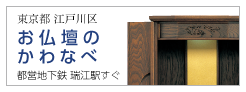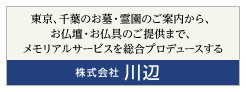法伝寺墓苑をご案内する、東京都江戸川区の石材店、株式会社川辺からのご案内
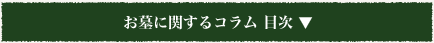
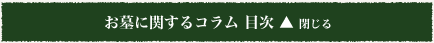
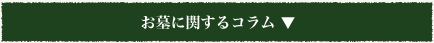
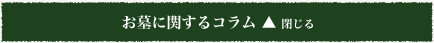
お線香(せんこう) について
お線香(せんこう) は、好まれる香りを出す材料を細かくして練り合わせ細い棒状にして乾燥させたお香のひとつです。
起源は古く、聖徳太子の時代に淡路島に香木「沈香」が漂着したのがはじまりとされています。以降、仏事や神事に使われるようになりましたが、現在のような棒状の線香の形になったのは江戸時代の初め頃からだといわれています。
お線香の材料
さまざまな原料の調合によって作られますが、主に天然原料で、その多くは漢方薬としても用いられています。代表的な原料としては、椨(たぶ)・沈香(じんこう)・白檀(びゃくだん)・桂皮(けいひ)・丁子(ちょうじ)・大茴香(だいういきょう)などがあります。
※この投稿は、墓苑に関する一般的な知識の普及を目標にしています。当寺に関するご案内ではございませんので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
浄土宗の年中行事(3)
4月7日
宗祖降誕会
法然上人が現在の岡山県で長承2(1133)年に生まれたことを喜び、その遺徳をしのぶものです。この日、浄土宗の各寺院では香華を供え、誕生に際しては天から上人が降りて来たという故事に因んで白旗が2本立てられます。
7月6日
記主忌
弘安10(1287)年に89歳で往生した浄土宗の第3祖、然阿良忠上人の命日の法要です。上人は、その送り名が「記主禅師」とされたことからもわかる通り、数多くの著述を行い、浄土宗の教学を大成させました。
※この投稿は、墓苑に関する一般的な知識の普及を目標にしています。当寺に関するご案内ではございませんので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
浄土宗 法伝寺 墓苑案内 - 川辺 Copyright(c) 2013.Hodenji Boen Annai .All Rights Reserved.