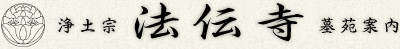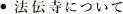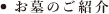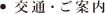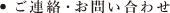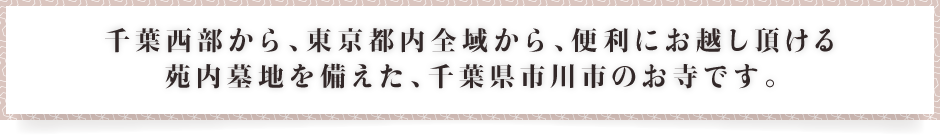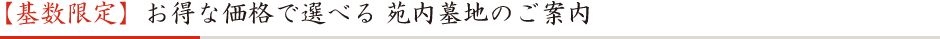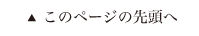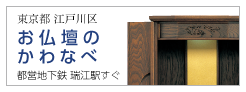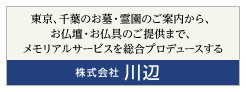法伝寺墓苑をご案内する、東京都江戸川区の石材店、株式会社川辺からのご案内
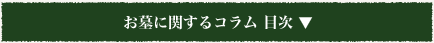
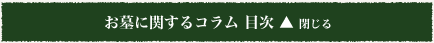
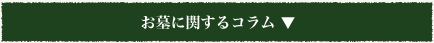
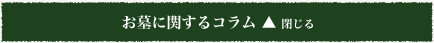
会社の経費・費用でお墓は建てられる?
いわゆる会社墓とする場合は、すべて会社の経費で建てることが出来ます。ただし、継承者は会社の代表者であり、代表者が交替する都度、変更の手続きをとる ことになります。また墓碑銘は「○○株式会社」とすることが多くなります。会社に貢献した創業者、社員等が希望すれば合葬できることが多いようです。
また、家代々のお墓や個人のお墓を会社の経費で建てることはできません。
【参考:ご葬儀での会社経費としての扱い】
経費にできる費用
・葬儀費用 ・火葬費用 ・新聞広告費用 ・通知状 ・会葬礼状 ・飲食費用
・会場費用 ・霊柩車・マイクロバスなどの車輌費用 ・お布施料(読経としての費用)
経費にきない費用
・お布施料(戒名としての費用) ・ご遺族からの香典返礼品
・仏壇・仏具購入費用 ・お墓購入費用 ・死亡診断書費用
洋型墓石
洋型墓石の種類
近年、公園墓地や芝生墓地の普及により建てられるようになった、高さが低く安定感のある形式のお墓です。日本古来から伝わってきたものではありませんが、墓石に刻む文字も家名だけでなく、好きな言葉や文字など自由なスタイルが特徴です。
主に、関東圏内の公園墓地や芝生墓地で多く取り入れられるようになりました。
デザインは、棹石の正面が地面と直角になっているストレートタイプや、お参りに来られる方の視線の位置を考慮して少し斜めに傾かせているオルガンタイプ、その他さまざまなデザインのものがあります。
洋型墓石の彫刻
正面文字には、もちろん家名を入れることもできますが、お好みのお言葉などを彫刻される事が増えているようです。
例えば、「和」「絆」「愛」「感謝」「ありがとう」「やすらぎ」「道」「慈」「夢」などが一般的です。
※この投稿は、墓苑に関する一般的な知識の普及を目標にしています。当寺に関するご案内ではございませんので、何卒ご了承下さいますようお願いいたします。
浄土宗 法伝寺 墓苑案内 - 川辺 Copyright(c) 2013.Hodenji Boen Annai .All Rights Reserved.